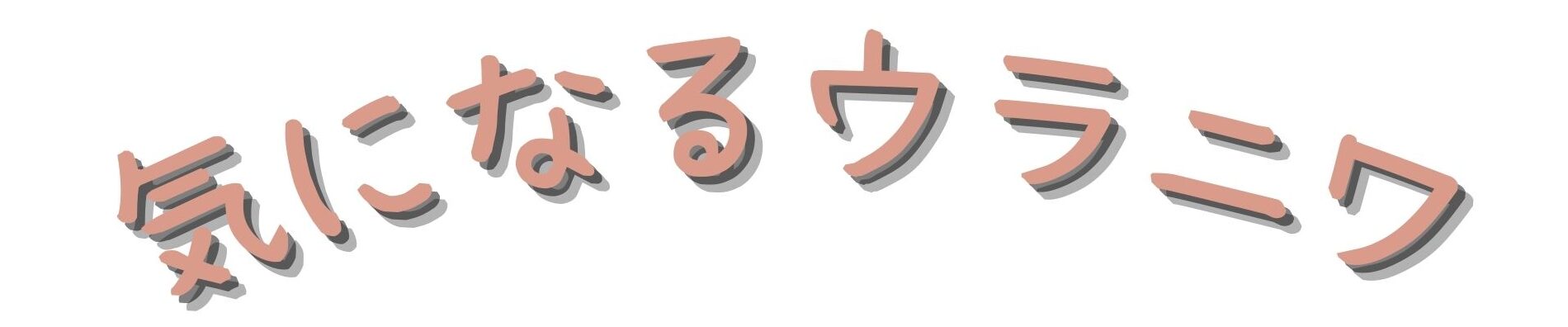小学生のうちはみんな同じぐらいの学力と思っている親は多いのではないでしょうか。
我が家の子供たち3人の学力を比べてみても、実は小学生のうちに何度が分かれ道が訪れています。
先に結論を伝えると、分かれ道となる学年は下の通り。
- 小学1年生
- 小学4年生
- 小学6年生
上記の学年の終盤に訪れると思っています。
今回の記事では、そんな勉強ができる子は周りの子といつから差が出てくるのか?
また、どんな学習方法をしているのかをまとめていきます。
- 勉強ができる子とできない子の差はいつからでる?
- 勉強ができる子にするには?
- 学習の差を埋める対策
勉強ができる子とそうでない子の差はいつから広がる?
一般的に、小学1~2年生の頃は内容が単純なものが多いのでクラスの全員が学校のテストで100が取れる学力は持っていると言われます。
世間一般では「10歳の壁」と言われるように、小4が分かれ道になってきます。
その理由は、小学3年生頃にだいたいの基礎学力が定着されるからです。
基礎学力が定着されていないと、10歳の壁にぶち当たることになってしまうんです。
小学校低学年(1〜3年生)ではまだ大きな差は出にくい?
冒頭でも、ちらっとお話ししたように、小学校の低学年では、まだ学習内容が基本的であるため、成長の差はそこまで大きくなりません。
主に「ひらがな・カタカナの読み書き」「簡単な計算」「生活習慣」が中心なので、学校の授業についていけないほどの学習はしていません。
これが、ほとんどの子の学力は一緒と考え大丈夫な理由です。
でも、我が子を見て感じるのは小学1年生のうちに基礎中の基礎はまだ身についていないと感じることがありました。
小学校の授業だけでは基礎中の基礎は身に付きにくいと感じています。
親が普段から子供の学力を判断して適切なサポートをしてあげるのが良いと思っています。
この時期にしっかりと身につけておきたい基礎を定着させておかないと後々の学習に影響が出てきてしまうからです。
では、何をどうサポートしてあげるといいのかですが、
それは、「家庭学習の習慣」と「生活習慣」です。
小学1年生と言えど、学校の宿題は基本的に毎日やる事になっているのではないでしょうか?
我が子が通う小学校でも小学校に入学して間もなく毎日の宿題が始まりました。
「毎日の宿題をしっかりやって先生に提出する」
「忘れ物をしないように子供が自ら管理できるように工夫する」
「先生の話をしっかり聞き、忘れそうなことは連絡帳に書いておく」
などの習慣を身に着けておくと、学年が上がった時にこの習慣が役に立つ時が来ると私は思っています。
小学4年生から学力が目に見えてわかる時期
小学4年生になると、勉強ができる子とそうではない子の差が目立ってきます。
その理由は、学習内容が小学4年生から一気に難しくなり、小学5年生になるとさらに難しくなってくるからです。
低学年での習慣が、4年生から目に見えてわかってきます。
では、どのぐらい難しくなってくるかというと、
この時期に「勉強のやり方がわからない」「授業についていけない」と感じると、学習に対して苦手意識が強くなり、余計に勉強が嫌いになってしまいます。
低学年のうちに身に着けた学習習慣があると、「勉強はやらなければならないもの」とわかっているので自主的に机に向かうようになり、問題が解けることが楽しいと思える子はどんどん知識を吸収していきます。
勉強ができる子は小学6年生で決定的に!
小学6年生になると、学力の差はさらに広がります。
勉強ができる子と苦手な子の違いは、「自分で学習計画を立てて学習を進める力があるかないか」です。
これまで勉強が苦手なままだった子は学習が嫌いなので、復習する習慣も身についていないのです。
小学6年生までは、中学生で本格的になる勉強の基礎をやっている時期なので、「小学校の内容が理解できているかどうか」で、中学になると学力はさらに落ちていきます。
ですが、学習習慣のない子でも基礎学力がある程度身についていれば中学でも挽回のチャンスはあると思っています。
小学6年生の時点で学力が低いと、中学に入ってから学力を上げることは本人が一番しんどいです。
我が子も、学力を上げることを目標としていますが、なんとか現状キープ止まりです。
勉強ができる子に育てたい!
勉強ができる子の特徴を見ていくと、いくつの特徴があることがわかります。
ですが、学習への意欲は子供の性格によるものが多く、親の気持ちだけではどうすることもできない事も多いです。
我が家の場合のご紹介していきます。
家庭学習の時間をつくる
勉強ができる子の多くは、低学年のうちから家庭学習の習慣がしっかり身についている子が多いように思います。
物分かりのいい子だったり、誰に対しても礼儀正しくしっかりしている子が多いのも特徴です。
そんな、誰が見ても賢そうな子の親は、学習の環境を整え、しっかりサポートしている家庭が多く、毎日決まった時間に勉強しているということです。
一方、我が家の子供たちは、机に向かうように声がけはしていますが、子供が自分のペースで学習する時間を決めています。
最終的に自分で学習する意識を持てるなら勉強も遊びもどちらでも良いのかなとも思うのですが、大事なのは「勉強するのが当たり前」の環境を作ることだと思っています。
読解力と理解力が高い子は伸びる
小さいころから、本の読み聞かせを親が行うと良いと言われていますよね。
こちら、本当にそうだったなと今更ながら実感しています。
文章を読む力が高い子は、国語だけでなく、算数・理科・社会でも成績が伸びやすいです。
- 要約できるか
- 読んだ内容を人に説明できるか
- 質問を立てて答えることができるか
- 多様なジャンルに触れてみる
家族とのお出かけの際に一緒に体験したことを話しあったり、教えたりして子供の知識を増やし手上げることも大事だなと思っています。
我が家の子はゲームが好きなこともあり、攻略本を読み漁っているタイプでしたが、説明文の学習の時にはとても役に立ったと感じています。
さらに、空間認識力を高めるゲームを取り入れたことも結果として、算数の図形に役にたちました。
ゲームが得意な子はゲーム感覚で学べる工夫としてみるとう良いかもしれません。
学びに対するポジティブな姿勢がある
基本的に勉強ってどの子も「できればやりたくない」「楽しくないけど仕方ないからやっている」という子がほとんどではないでしょうか。
でも、勉強ができる子は学ぶことに対してポジティブな感情を持っている子が多いんです。
それは、「できた!」を増やすことです。
基本的に子供って興味があることは率先してやりたがりますよね?
子供がやってみたいということは家庭の影響なども考えて無理のない範囲でやらせてみるのが良いなと感じています。
負けず嫌いなタイプの子や、勉強に自信がある子は、できない事があると悔しいと感じるので「どうして理解できないのか」を考え「どうすれば理解できるのか」を自分で考え、自分でインプットとアウトプットを繰り返し解決していく思考が身についているんだと思います。
何度も失敗をしてできた経験は自分への自信にもなりますよね。
学習の差を広げないための親の対策
小学生の学習の差を広げないためには、親がどれだけサポートできるかはやはり重要になってきます。
特に以下のポイントに注意すると、学習の遅れを防ぎ、子どもの学力を安定させやすくなります。
低学年のうちから学習習慣を徹底させたい
低学年のうちは、学習習慣を作ることが何よりも大切です。
- 短時間でも毎日コツコツ勉強する
- 宿題だけでなく、少しプラスの学習を取り入れる
低学年のうちは、集中力が短いのでたくさんの時間を家庭学習にあてる必要はなく、集中して何かをやる時間を作ってあげることで良いと思います。
「算数の計算プリントを1枚」とか「漢字を10個」だったり。
家庭学習するなら、学校で学習してきたことの復習をするのが知識の定着に繋がるので良いと思います。
学習のリズムができている子は、高学年になっても自然と勉強するようになります。
苦手を放置しない
苦手科目は早めに対策をしないと、学習の差が開く原因になります。
また、得意な科目があるならその科目に力を入れるとどんどん伸びることもあります。
- 計算が遅いなら、簡単な計算練習を毎日少しずつ
- 漢字が苦手なら、1日1つでもいいので練習
- 文章問題が苦手なら、一緒に問題を読んで考える習慣をつける
人は、時間がたつと記憶が曖昧になってきますよね。
苦手な科目ならなおさらな忘れていき、苦手は苦手なままなので、結果としてケアレスミスにもつながります。
習い事や塾の活用
学校の勉強だけでは不安な場合、学研教室や公文、家庭教師、通信教育などを検討するのも方法のひとつです。特に、
- 学習のペースを作るのが苦手な子には、定期的に通う学習教室が向いている
- 自宅でコツコツできる子には、タブレット学習や通信教育が合っている
生活リズムを整える
学習の差を防ぐには、生活リズムが安定していることも大事です。
- 睡眠時間をしっかり確保する
- 朝ごはんをしっかり食べる
- ゲームや動画の時間を管理する
などテレビやスマホから離れる環境をつくって集中できるスペースを確保するもの効果があります。
無理な詰め込みを避ける
勉強量を増やしすぎると嫌いになる子は多いです。
結果的に学力に差が出てしまうこともあるので楽しく続けられる量を意識するのがいいですね。
子供だけの遊びも大切にする
周りの友達と遊ぶことで、モチベーションが上がることもあります。
幼児期の頃は比較的親子で一緒に行動することが当たり前で生活してきましたが、小学生になると自分だけの時間や子供同士の時間が多くなります。
- 友達と一緒に公園へ行く
- 友達とゲームをする
学校との連携を大事にする
子どもの学習状況を把握するために、学校との連携も大切です。
- 通知表やテストの結果をしっかり確認する
- 個人面談を活用して先生からのアドバイスをもらう
- 家庭でできるサポートを先生と相談する
「今日学校でどんなことを習ったの?」など子供に話を聞いてみると、子供は思い出して説明することで理解が深まり記憶に残りますよね。
まとめ:勉強の差は小学4年生頃から広がるは本当だった!
学習の差を広げないためには、学習習慣をつけることも大切ですが、親ができる事はたくさんあります。
親子で一緒に体験したことはなかなか忘れないので、その体験の中に学習のようなものを取り入れてみたりするといいのではと思います。
どの方法が合うかは子どもによって違うので、試しながら工夫してみてくださいね!
最後までごらんいただきありがとうございました。
▶ママ友賢い付き合い方の適度な距離感のコツとは?断り方例文も解説!