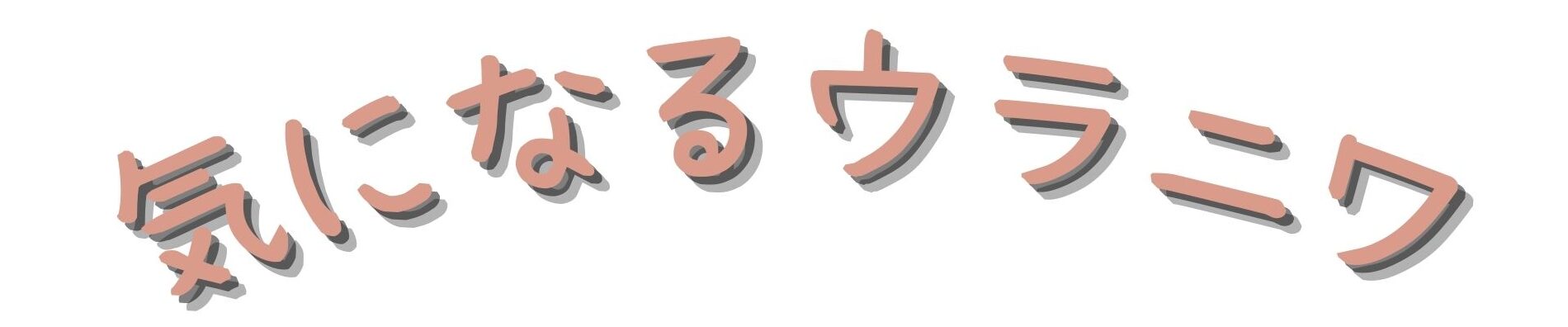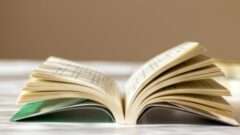我が家の子供は基本的に、リビング学習を取り入れて学習してきのですが、成長と共に次第に「集中できない」という問題が出てきました。
ただ、「うるさい環境で学習した方が集中力がつく」ということを耳にしたこともあるし、私もそう思いこんでいたのですが、どうやら集中できないには原因があったようです。
この記事では、私たちの体験を元に、リビング学習のメリット・デメリット、そして集中力を高めるための工夫をお話ししたいと思います。
- リビング学習はいつまで続けるべき?
- リビング学習で集中できない子の原因と改善方法
- リビング学習が向いている子の特徴
「学研教室なら、お子さまの『学ぶ力』が自然と育つ! 一人ひとりのペースに合わせた丁寧な指導で、学校の勉強がスムーズに理解できるようになり、自信とやる気がアップ!『わかった!できた!』の成功体験を積み重ねることで、学ぶ楽しさがどんどん広がります。
学研教室が近くにない場合や送迎が難しい人には、オンラインゃ通信講座もありますよ!!
\気になったらすぐ体験♪まずはお問合せ/
リビング学習はいつまで?目安は中学生以上!
リビング学習が向いていない年齢は、一般的には小学生高学年や中学生あたりに該当することが多いです。
以下の理由から、年齢によってはリビング学習が難しくなることがあります。
- 学習内容の難易度が上がる
- 自立した学習が求められる
- 思春期によるプライバシーの意識
- 長時間の学習が必要になる
学習内容の難易度が上がる
中学生になると、教科ごとに専門的な内容が増え、より深い理解や暗記が必要になります。
数学の証明問題や英語の長文読解など、集中力を要する勉強が増えるため、家族の会話や生活音があるリビングでは気が散りやすくなります。
我が家の体験談
小学生の頃はリビング学習で宿題をこなしていた子どもも、中学生になると「うるさい」「静かな方がやりやすい」と言い出しました。
特にテスト前は、自分の部屋にこもることが増えました。
自立した学習が求められる
中学生になると、学校の授業スピードが速くなり、予習・復習の重要性が増します。
自分で計画を立て、学習を進める必要があるため、親のサポートを前提としたリビング学習が合わなくなる場合があります。
我が家の体験談
「ママ、これどうやるの?」と聞いていた小学生時代と違い、中学生になってからは「自分でやるからいい」と言うことが増えました。
リビングでは親の目が気になるようで、勉強への意欲が下がることもありました。
そもそも、悲しいですが中学生になると親が教えられる範囲を超えていることがありますよね。
思春期によるプライバシーの意識
思春期になると、自分の考えを深めたり、1人で集中する時間を大切にしたくなります。
リビングだと家族の目が気になり、勉強中の姿を見られたくない、質問されたくない、と感じる子もいます。
我が家の体験談
中学生になった途端「見ないで」と言われるように。
テスト勉強中も「リビングだと落ち着かない」と言い、自分の部屋で勉強する時間が増えました。
長時間の学習が必要になる
中学生は宿題に加えて定期テストの勉強や部活との両立が必要になり、学習時間が長くなります。
リビングでは家族がくつろぎ始める時間帯と重なることが多く、集中しづらい環境になりがちです。
我が家の体験談
夕食後のリビングで勉強していたものの、テレビをつける家族と衝突することが増えました。
「静かにして」と言われる側もストレスを感じるため、最終的には自分の部屋で勉強するようになりました。
リビング学習で集中できない子の原因と対策
- 学習スペースを固定する
- 生活音をコントロールする
- 学習時間を決める
- 親の関わり方を工夫する
- 勉強とリラックスの切り替えを意識する
学習スペースを固定する
リビング学習で集中できない原因の一つは、学習場所が固定されていないことです。
毎回勉強する場所を変えると、子どもは環境に適応するためにエネルギーを使い、気が散りやすくなります。
そこで、学習スペースを固定することが重要です。
例えば、ダイニングテーブルの一角や専用の学習机を決め、毎回その場所で勉強をする習慣を作ると、精神的に「勉強モード」に切り替えやすくなります。
これにより、集中力が高まり、効率的に学習が進むようになります。
生活音をコントロールする
リビング学習で集中できない原因の一つは、生活音の影響です。
特にテレビやスマホの音は、子どもが学習に集中する妨げになります。
我が家でも、テレビを消し、スマホの通知音をオフにするようにしました。
また、無音だと落ち着かない子もいるので、適度なBGMを流す方法も試しました。
カフェミュージックやホワイトノイズが効果的で、周囲の音が気にならず、集中力を維持しやすくなりました。
家族全員で協力し、学習中は静かな環境を作ることが大切だと実感しています。
学習時間を決める
リビング学習で集中できる環境を作るためには、学習時間を決めることも重要です。
決まった時間に勉強を始めることで、子どもも「今は勉強する時間」と意識しやすくなります。
我が家では、学習時間を予め決めて、タイマーを使って時間を区切るようにしました。
最初は長時間の学習に集中できなかった子どもも、少しずつ時間を守るようになり、勉強に対する意識も変わってきました。
学習時間を決めることで、リズムよく勉強する習慣が身につき、学習効率も上がったと感じています。
親の関わり方を工夫する
リビング学習では、親の関わり方が子どもの集中力や学習意欲に大きく影響します。
親が近くにいることで、子どもは安心感を持ちつつも、適度な緊張感を感じることができます。
私は子どもが勉強しているとき、横で何かをしているけれども、できるだけ声をかけずに見守るようにしています。
時々、質問や相談があればサポートし、終わった後に一緒に振り返りをして、どんな点が良かったのか、どこを改善するべきかを話します。
このように、親が過剰に干渉せず、適度に関わることで、子どもの自主性や学習の意欲が育まれています。
勉強とリラックスの切り替えを意識する
リビング学習で勉強とリラックスの切り替えを意識することは、子どもの集中力を高めるために重要です。
長時間同じ場所で勉強をしていると、集中力が切れやすくなります。
私の場合、子どもが一定時間勉強した後は、短い休憩を取るようにしています。
例えば、15分集中して勉強したら5分間の休憩を設け、軽くおやつを食べたり、リビングでのんびりする時間を作ることを習慣にしています。
このように、勉強とリラックスを切り替えることで、気分転換ができ、再び勉強に集中しやすくなります。
また、休憩時にはリラックスできる環境を整えることも大切です。
リビング学習で集中力は本当につくのか?
まず、先に結論を先に言うと、うるさい環境でも集中できる子とできない子は真っ二つに分かれると我が家の子をみて感じています。
リビング学習を取り入れている家庭は多いですが、実際のところ、リビング学習が集中力の向上につながるかどうかは 「子どもの性格」「環境の工夫」「学習スタイル」 によって変わります。
リビング学習が良いと言われる理由には次のようなことがあります。
- 適度な雑音が集中力を鍛える
- 生活リズムが整い、学習の習慣化につながる
- 親が近くにいることで適度な緊張感が生まれる
適度な雑音が集中力を鍛える
リビングは家族の会話や生活音があるため、「完全な静寂」ではありません。
しかし、適度な雑音がある環境で勉強することで 「集中の持続力」 を鍛えることができるとも言われています。
我が家でもリビング学習を続けていますが、最初は「テレビの音や家事の音で集中できないのでは?」と心配でした。
ところが、意外にも子どもは雑音の中でも勉強に取り組めるようになりました。
これは、適度な環境音が脳を活性化し、集中力を高めるという研究とも一致しています。
カフェの雑音程度の音(約70デシベル)があると、脳が必要な情報を取捨選択し、注意力が鍛えられるそうです。
確かに我が子も、多少の話し声や生活音があっても気にせず勉強を続けられるようになりました。
リビング学習の雑音は、集中力を育てるトレーニングになっていると感じています。
生活リズムが整い、学習の習慣化につながる
我が家でもリビング学習を取り入れてから、子どもたちの生活リズムが徐々に整うようになりました。
最初は、学習の時間がバラバラでしたが、リビングでみんなが集まる時間に勉強をすることで、自然と勉強時間が日常の一部に組み込まれました。
特に、夕食前の時間帯に宿題をするようになったことで、決まった時間に勉強する習慣が身につきました。
親の目が届く環境だからこそ、集中して学習できるようになり、生活全体が規則正しくなったことを実感しています。
親が近くにいることで適度な緊張感が生まれる
親が近くにいることで、子どもは適度な緊張感を持ちながら学習に取り組むことができると言われています。
親の目があることで、だらけずに集中しやすくなるためです。
リビング学習では、自然と「見守られている」と感じることで、時間を無駄にせず、集中力を高める効果があります。
私の家でも、最初はリビングで勉強しているときに子どもが遊びたがっていましたが、私が近くで作業していることで、自然と「今は勉強する時間」と意識するようになり、やる気を持って取り組むようになりました。
親がそばにいることは、勉強への意識を高める大きな要因となります。
ただし、リビング学習が向いている子と向いていない子について、我が家の場合は2つに分かれました。
大きくわけると、「最初からそれなりの集中力を持っている子は向いていいる子」で、リビング学習が向いていない子は「自分の部屋であっても集中力が続かない」傾向にあります。
では、どんな子がリビング学習に向いている子なのか?
向いていないと感じた場合はそもそもリビング学習に適した環境にしていない場合もあるので次で解説していきます。
リビング学習が向いている子の特徴
- 親のサポートがあると安心する子
- 適度な雑音があっても集中できる子
- 勉強の習慣がまだ身についていない子
- 短時間で集中できる子
親のサポートがあると安心する子
リビング学習では、親が近くにいることで安心感を得られる子に向いています。
特に低学年のうちは、分からない問題をすぐに質問できる環境が学習意欲につながります。
親が近くにいることで、質問があった際に即対応でき、学習への不安やストレスを軽減できます。
また、親の存在は子どもの学習意欲を高める要因にもなります。
私の家でも、子どもが問題に直面したとき、すぐにアドバイスできるので、安心して勉強を続けることができています。
特に、小さな問題でも親が側にいると、子どもは解決できる自信を持ちやすいと感じました。
適度な雑音があっても集中できる子
適度な雑音があっても集中できる子は、外的な刺激をうまく無視したり、リズムを崩さずに作業を進められるタイプの子どもです。
こうした子どもは、雑音があっても自分の集中力を維持できるため、周囲の音に影響されにくいとされています。
私の家でも、リビング学習をする際、最初は雑音に敏感だった子どもが、少しずつ周囲の話し声やテレビの音を気にせず学習に集中できるようになりました。
子どもが自然に集中できるようになったのは、日常的にリビングで学習をすることで、雑音があっても集中力を養うことができたからだと感じています。
勉強の習慣がまだ身についていない子
自分の部屋で一人で勉強するのが難しい子には、リビングで「学習する習慣」をつけることが効果的です。
家族が近くにいることで、サボりにくくなるメリットもあります。
私の家でも、最初は勉強の時間を決めるのが難しかったのですが、リビング学習を始めてから、子どもは毎日決まった時間に自然に勉強する習慣が身につきました。
勉強を生活の一部として意識することで、習慣化が進んだと感じています。
短時間で集中できる子
短時間で集中できる子にリビング学習が向いている理由は、リビング学習が時間や環境に適した集中を促すからです。
リビングは他の部屋に比べて、適度な刺激があり、時間が限られることで集中を高める効果があると言われています。
例えば「学校の宿題だけはリビングでやる」と決めると、ダラダラせずに済みます。
我が家でも、子どもは長時間の勉強に疲れやすかったのですが、リビング学習を取り入れてから、集中して短時間で効率よく勉強できるようになりました。
休憩を挟みながら、集中とリフレッシュをうまくバランスさせることができました。
リビング学習を続けるかどうかの見極めポイント
✔ 集中できているか?
✔ 自主的に学習できているか?
✔ 家族の生活リズムと合っているか?
✔ 成績や理解度に影響が出ていないか?
集中できているか?
✅ リビングでも気が散らず、学習に取り組めているか?
✅ テレビや家族の会話があっても、問題なく勉強を続けられるか?
→ 集中できているなら継続OK!
→ 気が散っているなら、自室学習を検討するタイミング!
我が家の体験談
低学年のうちは「静かすぎると落ち着かない」と言っていた子どもも、中学年になり「家族の話し声が気になる」と言うようになりました。宿題のミスも増えてきたので、自室で勉強する日を増やしていきました。
自主的に学習できているか?
✅ 親の声かけなしでも机に向かう習慣がついているか?
✅ 親がいなくても、学習を続けられるか?
→ 自主的に学習できているなら、環境を問わずOK!
→ 声かけがないと取り組まないなら、親の関与を考慮しつつ見直しを!
我が家の体験談
小学生のうちは「ママが横にいてくれると安心」と言っていたので、リビング学習を続けていました。しかし、中学生になり「1人でやるからいい」と言うことが増えたので、徐々に自室学習へ移行しました。
家族の生活とバッティングしていないか?
✅ 勉強時間と家族の過ごし方がぶつかっていないか?
✅ 「静かにして」と何度も言う状況になっていないか?
→ 生活リズムに合っているなら継続OK!
→ 家族と衝突が増えているなら、別の場所を考えた方がスムーズ!
我が家の体験談
夕食後にリビングで勉強していましたが、テレビを見たい家族との衝突が増えたため、「夕食後以降は自室で勉強」とルールを決めたことで、お互いストレスなく過ごせるようになりました。
「学研教室なら、お子さまの『学ぶ力』が自然と育つ! 一人ひとりのペースに合わせた丁寧な指導で、学校の勉強がスムーズに理解できるようになり、自信とやる気がアップ!『わかった!できた!』の成功体験を積み重ねることで、学ぶ楽しさがどんどん広がります。
学研教室が近くにない場合や送迎が難しい人には、オンラインゃ通信講座もありますよ!!
\気になったらすぐ体験♪まずはお問合せ/
まとめ
小学生のうちは親のサポートを受けながらリビング学習が効果的なこともありますが、中学生になると「学習内容の難易度」「自立心の成長」「プライバシー意識」「長時間の学習」の観点から、リビングよりも個室学習の方が向いてくることが多いです。
ただし、個人差があるため、リビング学習が合う子もいます。
「リビングの方が落ち着く」「親が近くにいると安心する」などの理由で続けられるなら、必ずしも部屋での学習にこだわる必要はありません。
子どもの学習スタイルに合わせて、適切な環境を整えることが大切です。
最後までごらんいただきありがとうございました。